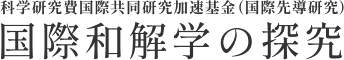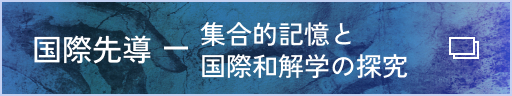和解学の目指すものとその起源
和解学創成プロジェクトは、日本を拠点とする多くの研究者を結集させ、東アジアにおいて頻発する歴史紛争を克服すべく組織されました。目指すところは、国民という匿名の集団が人々の心の中に想像されているのと同じように、国民と国民との和解もまた、同じように想像され得る時代をつくることです。しかし、それは市民としての国籍を超えた和解を無視するものではありません。むしろ、それを促進する環境を整えるためにも、国民的和解の想像可能性に取り組む必要があると考えています。本プロジェクトは、そのために必要な社会的な条件を学問的に探求しつつ、社会への知的インフラの提供という貢献も行ってまいります。
最終的には、ネーションが人々の心の中に想像されているように、ネーション・国民相互の和解をも同時に想像することができるようになる社会的条件を分析・探求し、それと同時に、その前提となる知的物的インフラのあり方をも考察したいと思います。それによって世界的な知的共同体のすそ野を拡大しながら、和解に貢献し得る知的共同体の責務を積極的に果たし、社会一般へ新たな学問の成果を還元してまいります。
その目玉の一つとして取り組んでいるのが「東アジア歴史紛争和解事典」です。これは歴史をめぐる紛争について、第一線で活躍する研究者・専門家が、第1次資料へのリンクを豊富に盛り込みながら、わかりやすくウェブサイト上で発信せんとするものです。こうした作業の上に、出版と知的ネットワークを構築しつつ、新しい学問領域としての和解学を築いていくのが本プロジェクトの最終目的です。
「和解学」というネーミングは、早稲田大学で大型プロジェクトを代表されてきた毛里和子先生によるものです。しかし、文部科学省の「新領域プログラム」に応募して「和解のための国際関係学」を創設しようとする試みは、波多野澄雄先生を代表に2008年度から続けられてきました。こうした先人の努力を土台として、この和解学創成プロジェクトは2017年7月から本格的にスタートしました。和解学は、国民を単位とする世界を認識しつつも、それに静かに向き合いながら、各分野を横断してその変化をとらえるための能動的な学問として展開されます。それは、今後の世界がどこへ向かっていくのか、その方向をも左右するような新たな学問として、進化を続けていくものとなるでしょう。
本プロジェクトをよろしくお願い申し上げます。
和解学の具体的方策と研究組織
和解学創成の手法は、東アジア固有の歴史的社会的文脈を学際的手法で把握し、その文脈に即したものへと移行期正義論、ならびに紛争解決学を進化させることを核としています。その際には、全世界を対象にアーネスト・ゲルナー、アントニー・スミス、ベネディクト・アンダーソンなどの手によって展開されてきたナショナリズム理論と、東アジアにおいて急速に進められた現実の国民国家化や民主化を中心とする地域研究との接合が大きなテーマとなります。この上に、広くて深い「和解」学の基盤を築きたいと考えています。
東アジア発の和解についての学知を新しく世界に向けて発信するべく、領域創成のための計画研究班を配置しました。
班の基本構成は、ディシプリンで分けるのではなく、分析の焦点を当てる四つの研究対象に即して分けています。
実践活動を実証分析の対象とするのが政治・外交班と市民運動班、表象や言説を分析の焦点とするのが歴史家ネットワーク班と和解文化・記憶班です。こうした実践と表象レベルを結んで、東アジア固有の歴史的文化的特性の中に正義のあり方を総合的に探るのが思想・理論班です。そして総括班は、和解学の成果を国際的に発信しつつ、普遍的な理論へと高めながら、和解の想像を可能とせしめる社会的条件の探求へと向かって5班の研究活動の国内的国際的連携を行ってまいります。

領域代表
浅野豊美(早稲田大学政治経済学術院教授)