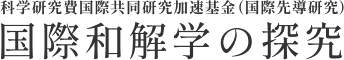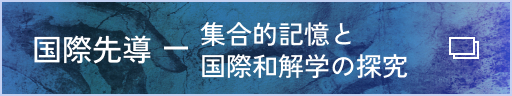「日朝関係に対する韓国の影響」宮本悟
1. 日本社会における北朝鮮のイメージ
日本と国交がない国連加盟国は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)だけである。そればかりか、北朝鮮は日本の周辺国であり、日本にとって軍事的な脅威となっている。日本社会における北朝鮮に対するイメージも最悪である。内閣府の2021年の「外交に関する世論調査」による「北朝鮮への関心事項」によれば、日本社会における北朝鮮への関心は、「日本人拉致問題」、「ミサイル問題」、「核問題」でトップ3を占めている 。この調査は2000年から始まったが、2000年の「外交に関する世論調査」による「北朝鮮への関心事項」では、「日本人拉致問題」、「ミサイル問題」、「食糧支援問題」でトップ3を占めていた。「食糧支援問題」と「核問題」が入れ替わっただけで、イメージが悪いことに変わりない 。
現代の日本社会における北朝鮮に対するイメージが概して悪いことは間違いないのだが、そもそもどうして悪いのであろうか。日本人拉致問題やミサイル問題は、冷戦後に日本社会で関心を持たれた問題である。冷戦時代からイメージが悪かったとすれば、他の原因があるはずである。その原因ついて、よく話題にあがるのは、北朝鮮は閉鎖的で情報が入ってこないからとか、北朝鮮は共産圏だからとか、非人道的だからというものがある。北朝鮮の特徴として当たっている部分もあるが、それが北朝鮮のイメージの悪さの理由とは言い難い。
情報がないというのは理由ではないだろう。情報があるからこそイメージが悪くなることもあり、情報がないからこそイメージが良くなることもあるからである。北朝鮮が非人道的というのは、冷戦後に広まった理解であって、冷戦時代にそれを指摘する論調はあまりなかった。また共産圏だからというのも、あまり理由にならない。戦後日本外交を俯瞰すると、冷戦時代、日本は共産圏との関係改善にかなり努力してきた。1950年代後半の鳩山一郎政権や岸信介政権では、吉田茂政権とは異なって、自主外交路線をとってソ連との国交正常化を実現し、北朝鮮への帰国事業にも協力した。その後の自民党政権も、共産圏との国交正常化を続けていった。
冷戦時代に、日本社会での北朝鮮のイメージを形成していたのは、韓国の影響ではないだろうか。冷戦時代は、南北朝鮮ともに非民主主義体制であって、どちらも日本社会でイメージが良かったとは思えない。しかし、韓国の状況を見て、韓国よりは北朝鮮のイメージが悪いとか、韓国よりは北朝鮮のイメージが良いとか、韓国と比較することで北朝鮮のイメージができあがっていったのかも知れない。
外交レベルでも、日朝関係は韓国に大きな影響を受けてきた。冷戦時代、日韓関係が発展すれば北朝鮮がそれを批判し、日朝関係が発展すれば韓国がそれを批判していた。日韓関係と日朝関係はトレードオフの関係であった。それが崩れ始めたのは冷戦後になってからである。冷戦後、韓国の影響から外れた日朝関係は、日本社会の北朝鮮に対するイメージによる世論に大きな影響を受けることになった。それを俯瞰してみよう。
2. 冷戦時代
1951年10月20日の予備会談から始まった日韓国交正常化交渉が暗礁に乗り上げ、自主外交路線を志向する日本民主党(後の自由民主党)の鳩山一郎政権が1954年12月10日に誕生すると、北朝鮮の外務相である南日が1955年2月25日に声明を発表して日朝国交正常化に意欲を見せた。日韓国交正常化を阻止して、北朝鮮が日本と国交を締結しようとしたのである。これに対して、韓国は批判を強めたが、中国の大連を通じた日朝貿易は始まることになった。
さらに、北朝鮮は、在日朝鮮人の帰国を推進したため、1959年8月13日に在日朝鮮人の帰還に関する日朝赤十字協定が締結されて、在日朝鮮人の北朝鮮への帰国事業が始まった。すると、在日朝鮮人の韓国への帰国を拒否していたにもかかわらず、韓国の李承晩政権は暴力によって帰国事業を妨害しようとした。12月4日に発覚した新潟日赤センター爆破未遂事件は、在日朝鮮人の北朝鮮への帰国事業を妨害するために、李承晩政権が日本で起こそうとしたテロ事件の一つであった。
当時の日本社会では、韓国の李承晩政権のイメージが悪かったために、北朝鮮のイメージが相対的に良かったのではないだろうか。もちろん、朝鮮半島に対する国民の意識調査などが、1950年代当時に日本になかったので、はっきりとは言えない。とはいえ、当時の新聞各紙の報道は帰国事業におおむね好意的であった。また、1962年に公開された浦山桐郎監督のデビュー作であり、1962年キネマ旬訪ベスト・テン第2位になった『キューポラのある街』(吉永小百合主演)で、北朝鮮への帰国事業について肯定的なイメージで描かれていたことから、当時は北朝鮮にそこまで悪いイメージがあったとは思えない。現在では、帰国事業を肯定的に捉えたとして批判の的にされることがある『キューポラのある街』であるが、当時の日本社会では自然に受け入れられる内容であったからこそ、人気があったのであろう。
しかし、外交レベルではそうはいかない。アメリカの同盟国であった日本にとって、北朝鮮よりも韓国の方が重要であったことは間違いないだろう。韓国がアメリカの同盟国であるからである。冷戦時代を通じて日本が北朝鮮と国交正常化する選択肢はなかった。
韓国で李承晩政権が崩壊した後、日韓国交正常化交渉が進むと、反対に北朝鮮の日本批判は強まった。1965年2月22日に日韓基本条約が締結された頃になると、北朝鮮では日本を軍国主義として批判し始めた。その後は、冷戦時代を通じて、日本政府は、韓国との関係に配慮したので、日朝関係は貿易や民間レベルの交流に止まった。ただし、冷戦時代でも、野党である日本共産党や日本社会党、公明党の議員の訪朝は続いた(ただし、中ソ対立の最中、1960年代後半に日本共産党は朝鮮労働党と対立し始めたので、日本共産党の議員の訪朝は1970年代にはなくなり、現在の北朝鮮では日本共産党との交流は歴史から消されている)。冷戦時代は、日本の政権与党が韓国との友好関係を維持しながら、野党の一部は北朝鮮との交流を続けるという姿勢を取り続けていたのである。日韓国交正常化後、韓国の情報は比較的日本社会に入ってきていたので、日本社会でも、韓国に比べて北朝鮮のイメージが悪いとか、韓国に比べて北朝鮮のイメージが良いというように分かれていたのではないだろうか。
それらを裏付けるアンケート調査がないでもない。読売新聞社が日韓基本条約締結前後である1964年4月3~5日と1965年11月2~4日に興味深いアンケート調査を実施した。回答者に好きな国と嫌いな国を挙げるというものである。1964年4月に韓国を嫌いな国として挙げた回答者は約9%であったが、1965年11月には約3%であった。1964年4月に北朝鮮を嫌いな国として挙げた回答者は約5%であったが、1965年11月には約2%であった。これだけを見れば、もともと北朝鮮よりも韓国が嫌われていて、日韓基本条約締結後にはその差が縮まっただけと思われる。しかし、1964年4月に韓国を好きな国として挙げた回答者は約1%であり、1965年11月には約0%であった。1964年4月に北朝鮮を好きな国として挙げた回答者は約0%であり、1965年11月にも約0%であった。ここから考えられるのは、南北朝鮮ともに日本では好感度が非常に低く、韓国と北朝鮮のどちらかが嫌いかで、嫌いではない一方に相対的に好感を持つ程度だったと思われる。日韓基本条約締結前は、北朝鮮よりも韓国を嫌いな人たちが多かったため、北朝鮮の方が比較的好感が持たれていたのではないだろうか。
3. 冷戦後
1988年7月7日に韓国の盧泰愚大統領が「特別宣言」で、北朝鮮が日本との関係を改善するための協力を行なう用意があると発表すると、1988年8月1日に総理大臣である竹下登が第113回国会衆議院本会議の国会答弁で以下のように語った。これが冷戦時代の日本の対朝政策をよく示している。
「我が国と北朝鮮との間に外交関係はございませんが、我が国としては、韓国との友好協力関係の増進を大前提としつつ、北朝鮮とも経済、文化等の分野における民間レベルの交流を積み重ねていくことが基本方針であります。なお、去る7月7日の盧泰愚大統領の特別宣言を受けて、我が国としても、関係諸国と緊密に協調の上、韓国と中ソの交流との均衡化に配慮しながら、日朝関係の改善を積極的に進めていきたいとの考えを示したところであります」
まだこの時点では、日朝国交正常化の意図があることを日本政府は表明していなかったが、韓国が日朝国交正常化に協力すると宣言したことで、日本でも日朝国交正常化の機運が高まった。1989年3月30日に竹下登が第114回国会衆議院予算委員会の国会答弁で日朝国交正常化の意図があることを表明した。この国会答弁の原稿は、当時、外務相北東アジア課長であった田中均が書いたものであったという。よく知られているように、田中均は後に日朝首脳会談を実現させた立役者である。
1990年9月24日から28日まで、自由民主党代表団(金丸信団長)と日本社会党代表団(田辺誠団長)が北朝鮮を訪問して、同年11月中に国交正常化のための外交交渉を開始することなどを盛り込んだ「日朝関係に関する日本の自由民主党、日本社会党、朝鮮労働党の共同宣言」が9月28日に発表された。実際に1990年11月から12月に3回の予備会談が開催されたことを皮切りに、日朝国交正常化交渉が始まった。その後の日朝国交正常化交渉については「東アジア歴史紛争和解事典」の「日朝国交正常化交渉」に書かれているので、割愛したい。
韓国が日朝関係改善化に協力すると宣言したので、日朝関係に対する韓国の影響はなくなるはずであったが、冷戦後に日朝関係における韓国の影響がすぐになくなったわけではない。韓国にとって日朝関係の改善よりも、南北関係の改善が先行することが前提だった。北朝鮮に対する食糧援助でもそうであった。食糧難に見舞われた北朝鮮が1995年に初めて西側諸国に支援を要請したが、それが日本であった。訪日中の李成禄・朝鮮国際貿易促進委員会委員長が、1995年5月26日に渡辺美智雄・元副総理と会談し、天候不順のため「コメを一定期間貸してもらいたい」と正式に要請した。しかし、韓国政府が先に食糧援助すべきであるとの立場を日本側に伝達し、先に韓国がコメを援助し、その次に日本が援助することになった。韓国は、第1回分としてコメ15万トンを無償援助することになり、6月25日に第一陣が出港した。日本は、有償15万トンと無償15万トンのコメを援助することになり、7月19日に第1陣が東京を出航した。韓国の要請によって、韓国よりも約1ヶ月遅らせることになったのである。
日本社会において、北朝鮮のイメージが急に悪化したのは、1998年8月31日のいわゆるテポドン発射実験からであると考えられている(北朝鮮の発表では人工衛星打ち上げ)。日本列島の上空を超えた発射実験によって、日本は一時的に朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)への資金拠出を拒んだ。日本のメディアでも、北朝鮮のミサイル問題について大きな関心と怒りを呼んだ。前年である1997年3月25日に「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」が結成され、4月15日に超党派国会議員の「北朝鮮拉致疑惑日本人救援議員連盟」が結成されたことで、拉致疑惑問題も注目を集め始めた。冒頭で紹介した2000年の「外交に関する世論調査」による「北朝鮮への関心事項」で、拉致疑惑問題やミサイル問題が北朝鮮に対する最も重要な関心事項になったのは、このためである。「食糧支援問題」が3つ目の関心事項になったのは、日本社会の北朝鮮に対するイメージが悪化したにもかかわらず、日本政府が2000年に2回わたって計60万トンのコメを北朝鮮に無償で援助したからである。
日朝関係における韓国の影響がほとんどなくなり始めたのは、この頃からである。日朝関係は、韓国よりも、日本社会の北朝鮮に対するイメージとそれに伴う世論の高まりに影響されるようになった。2000年6月に開催された最初の南北首脳会談でも、日本社会の北朝鮮に対するイメージは変わらなかった。2002年9月17日に第1回日朝首脳会談が開催されたが、そこで拉致問題が疑惑ではなく実際に発生した事件であることが明らかになると、北朝鮮に対するイメージはさらに悪化することになった。
以降、日本社会における北朝鮮のイメージは、核問題も加わっており、良くなることは考えにくい。冷戦後、日朝関係における韓国の影響はほとんどなくなったが、それは日本社会の北朝鮮に対するイメージが悪化したためであって、たとえ日本政府が努力したところで、日朝関係はより悪くなることを避けられなかった。この状態は、おそらくこれからも続くことになるだろう。
「外交に関する世論調査」(内閣府)(https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-gaiko/zh/z19.html)(2022年2月11日アクセス)
「外交に関する世論調査」(内閣府)(https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikou_01/images/zu37.gif)(2022年2月11日アクセス
日本と国交がない国連加盟国は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)だけである。そればかりか、北朝鮮は日本の周辺国であり、日本にとって軍事的な脅威となっている。日本社会における北朝鮮に対するイメージも最悪である。内閣府の2021年の「外交に関する世論調査」による「北朝鮮への関心事項」によれば、日本社会における北朝鮮への関心は、「日本人拉致問題」、「ミサイル問題」、「核問題」でトップ3を占めている 。この調査は2000年から始まったが、2000年の「外交に関する世論調査」による「北朝鮮への関心事項」では、「日本人拉致問題」、「ミサイル問題」、「食糧支援問題」でトップ3を占めていた。「食糧支援問題」と「核問題」が入れ替わっただけで、イメージが悪いことに変わりない 。
現代の日本社会における北朝鮮に対するイメージが概して悪いことは間違いないのだが、そもそもどうして悪いのであろうか。日本人拉致問題やミサイル問題は、冷戦後に日本社会で関心を持たれた問題である。冷戦時代からイメージが悪かったとすれば、他の原因があるはずである。その原因ついて、よく話題にあがるのは、北朝鮮は閉鎖的で情報が入ってこないからとか、北朝鮮は共産圏だからとか、非人道的だからというものがある。北朝鮮の特徴として当たっている部分もあるが、それが北朝鮮のイメージの悪さの理由とは言い難い。
情報がないというのは理由ではないだろう。情報があるからこそイメージが悪くなることもあり、情報がないからこそイメージが良くなることもあるからである。北朝鮮が非人道的というのは、冷戦後に広まった理解であって、冷戦時代にそれを指摘する論調はあまりなかった。また共産圏だからというのも、あまり理由にならない。戦後日本外交を俯瞰すると、冷戦時代、日本は共産圏との関係改善にかなり努力してきた。1950年代後半の鳩山一郎政権や岸信介政権では、吉田茂政権とは異なって、自主外交路線をとってソ連との国交正常化を実現し、北朝鮮への帰国事業にも協力した。その後の自民党政権も、共産圏との国交正常化を続けていった。
冷戦時代に、日本社会での北朝鮮のイメージを形成していたのは、韓国の影響ではないだろうか。冷戦時代は、南北朝鮮ともに非民主主義体制であって、どちらも日本社会でイメージが良かったとは思えない。しかし、韓国の状況を見て、韓国よりは北朝鮮のイメージが悪いとか、韓国よりは北朝鮮のイメージが良いとか、韓国と比較することで北朝鮮のイメージができあがっていったのかも知れない。
外交レベルでも、日朝関係は韓国に大きな影響を受けてきた。冷戦時代、日韓関係が発展すれば北朝鮮がそれを批判し、日朝関係が発展すれば韓国がそれを批判していた。日韓関係と日朝関係はトレードオフの関係であった。それが崩れ始めたのは冷戦後になってからである。冷戦後、韓国の影響から外れた日朝関係は、日本社会の北朝鮮に対するイメージによる世論に大きな影響を受けることになった。それを俯瞰してみよう。
2. 冷戦時代
1951年10月20日の予備会談から始まった日韓国交正常化交渉が暗礁に乗り上げ、自主外交路線を志向する日本民主党(後の自由民主党)の鳩山一郎政権が1954年12月10日に誕生すると、北朝鮮の外務相である南日が1955年2月25日に声明を発表して日朝国交正常化に意欲を見せた。日韓国交正常化を阻止して、北朝鮮が日本と国交を締結しようとしたのである。これに対して、韓国は批判を強めたが、中国の大連を通じた日朝貿易は始まることになった。
さらに、北朝鮮は、在日朝鮮人の帰国を推進したため、1959年8月13日に在日朝鮮人の帰還に関する日朝赤十字協定が締結されて、在日朝鮮人の北朝鮮への帰国事業が始まった。すると、在日朝鮮人の韓国への帰国を拒否していたにもかかわらず、韓国の李承晩政権は暴力によって帰国事業を妨害しようとした。12月4日に発覚した新潟日赤センター爆破未遂事件は、在日朝鮮人の北朝鮮への帰国事業を妨害するために、李承晩政権が日本で起こそうとしたテロ事件の一つであった。
当時の日本社会では、韓国の李承晩政権のイメージが悪かったために、北朝鮮のイメージが相対的に良かったのではないだろうか。もちろん、朝鮮半島に対する国民の意識調査などが、1950年代当時に日本になかったので、はっきりとは言えない。とはいえ、当時の新聞各紙の報道は帰国事業におおむね好意的であった。また、1962年に公開された浦山桐郎監督のデビュー作であり、1962年キネマ旬訪ベスト・テン第2位になった『キューポラのある街』(吉永小百合主演)で、北朝鮮への帰国事業について肯定的なイメージで描かれていたことから、当時は北朝鮮にそこまで悪いイメージがあったとは思えない。現在では、帰国事業を肯定的に捉えたとして批判の的にされることがある『キューポラのある街』であるが、当時の日本社会では自然に受け入れられる内容であったからこそ、人気があったのであろう。
しかし、外交レベルではそうはいかない。アメリカの同盟国であった日本にとって、北朝鮮よりも韓国の方が重要であったことは間違いないだろう。韓国がアメリカの同盟国であるからである。冷戦時代を通じて日本が北朝鮮と国交正常化する選択肢はなかった。
韓国で李承晩政権が崩壊した後、日韓国交正常化交渉が進むと、反対に北朝鮮の日本批判は強まった。1965年2月22日に日韓基本条約が締結された頃になると、北朝鮮では日本を軍国主義として批判し始めた。その後は、冷戦時代を通じて、日本政府は、韓国との関係に配慮したので、日朝関係は貿易や民間レベルの交流に止まった。ただし、冷戦時代でも、野党である日本共産党や日本社会党、公明党の議員の訪朝は続いた(ただし、中ソ対立の最中、1960年代後半に日本共産党は朝鮮労働党と対立し始めたので、日本共産党の議員の訪朝は1970年代にはなくなり、現在の北朝鮮では日本共産党との交流は歴史から消されている)。冷戦時代は、日本の政権与党が韓国との友好関係を維持しながら、野党の一部は北朝鮮との交流を続けるという姿勢を取り続けていたのである。日韓国交正常化後、韓国の情報は比較的日本社会に入ってきていたので、日本社会でも、韓国に比べて北朝鮮のイメージが悪いとか、韓国に比べて北朝鮮のイメージが良いというように分かれていたのではないだろうか。
それらを裏付けるアンケート調査がないでもない。読売新聞社が日韓基本条約締結前後である1964年4月3~5日と1965年11月2~4日に興味深いアンケート調査を実施した。回答者に好きな国と嫌いな国を挙げるというものである。1964年4月に韓国を嫌いな国として挙げた回答者は約9%であったが、1965年11月には約3%であった。1964年4月に北朝鮮を嫌いな国として挙げた回答者は約5%であったが、1965年11月には約2%であった。これだけを見れば、もともと北朝鮮よりも韓国が嫌われていて、日韓基本条約締結後にはその差が縮まっただけと思われる。しかし、1964年4月に韓国を好きな国として挙げた回答者は約1%であり、1965年11月には約0%であった。1964年4月に北朝鮮を好きな国として挙げた回答者は約0%であり、1965年11月にも約0%であった。ここから考えられるのは、南北朝鮮ともに日本では好感度が非常に低く、韓国と北朝鮮のどちらかが嫌いかで、嫌いではない一方に相対的に好感を持つ程度だったと思われる。日韓基本条約締結前は、北朝鮮よりも韓国を嫌いな人たちが多かったため、北朝鮮の方が比較的好感が持たれていたのではないだろうか。
3. 冷戦後
1988年7月7日に韓国の盧泰愚大統領が「特別宣言」で、北朝鮮が日本との関係を改善するための協力を行なう用意があると発表すると、1988年8月1日に総理大臣である竹下登が第113回国会衆議院本会議の国会答弁で以下のように語った。これが冷戦時代の日本の対朝政策をよく示している。
「我が国と北朝鮮との間に外交関係はございませんが、我が国としては、韓国との友好協力関係の増進を大前提としつつ、北朝鮮とも経済、文化等の分野における民間レベルの交流を積み重ねていくことが基本方針であります。なお、去る7月7日の盧泰愚大統領の特別宣言を受けて、我が国としても、関係諸国と緊密に協調の上、韓国と中ソの交流との均衡化に配慮しながら、日朝関係の改善を積極的に進めていきたいとの考えを示したところであります」
まだこの時点では、日朝国交正常化の意図があることを日本政府は表明していなかったが、韓国が日朝国交正常化に協力すると宣言したことで、日本でも日朝国交正常化の機運が高まった。1989年3月30日に竹下登が第114回国会衆議院予算委員会の国会答弁で日朝国交正常化の意図があることを表明した。この国会答弁の原稿は、当時、外務相北東アジア課長であった田中均が書いたものであったという。よく知られているように、田中均は後に日朝首脳会談を実現させた立役者である。
1990年9月24日から28日まで、自由民主党代表団(金丸信団長)と日本社会党代表団(田辺誠団長)が北朝鮮を訪問して、同年11月中に国交正常化のための外交交渉を開始することなどを盛り込んだ「日朝関係に関する日本の自由民主党、日本社会党、朝鮮労働党の共同宣言」が9月28日に発表された。実際に1990年11月から12月に3回の予備会談が開催されたことを皮切りに、日朝国交正常化交渉が始まった。その後の日朝国交正常化交渉については「東アジア歴史紛争和解事典」の「日朝国交正常化交渉」に書かれているので、割愛したい。
韓国が日朝関係改善化に協力すると宣言したので、日朝関係に対する韓国の影響はなくなるはずであったが、冷戦後に日朝関係における韓国の影響がすぐになくなったわけではない。韓国にとって日朝関係の改善よりも、南北関係の改善が先行することが前提だった。北朝鮮に対する食糧援助でもそうであった。食糧難に見舞われた北朝鮮が1995年に初めて西側諸国に支援を要請したが、それが日本であった。訪日中の李成禄・朝鮮国際貿易促進委員会委員長が、1995年5月26日に渡辺美智雄・元副総理と会談し、天候不順のため「コメを一定期間貸してもらいたい」と正式に要請した。しかし、韓国政府が先に食糧援助すべきであるとの立場を日本側に伝達し、先に韓国がコメを援助し、その次に日本が援助することになった。韓国は、第1回分としてコメ15万トンを無償援助することになり、6月25日に第一陣が出港した。日本は、有償15万トンと無償15万トンのコメを援助することになり、7月19日に第1陣が東京を出航した。韓国の要請によって、韓国よりも約1ヶ月遅らせることになったのである。
日本社会において、北朝鮮のイメージが急に悪化したのは、1998年8月31日のいわゆるテポドン発射実験からであると考えられている(北朝鮮の発表では人工衛星打ち上げ)。日本列島の上空を超えた発射実験によって、日本は一時的に朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)への資金拠出を拒んだ。日本のメディアでも、北朝鮮のミサイル問題について大きな関心と怒りを呼んだ。前年である1997年3月25日に「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」が結成され、4月15日に超党派国会議員の「北朝鮮拉致疑惑日本人救援議員連盟」が結成されたことで、拉致疑惑問題も注目を集め始めた。冒頭で紹介した2000年の「外交に関する世論調査」による「北朝鮮への関心事項」で、拉致疑惑問題やミサイル問題が北朝鮮に対する最も重要な関心事項になったのは、このためである。「食糧支援問題」が3つ目の関心事項になったのは、日本社会の北朝鮮に対するイメージが悪化したにもかかわらず、日本政府が2000年に2回わたって計60万トンのコメを北朝鮮に無償で援助したからである。
日朝関係における韓国の影響がほとんどなくなり始めたのは、この頃からである。日朝関係は、韓国よりも、日本社会の北朝鮮に対するイメージとそれに伴う世論の高まりに影響されるようになった。2000年6月に開催された最初の南北首脳会談でも、日本社会の北朝鮮に対するイメージは変わらなかった。2002年9月17日に第1回日朝首脳会談が開催されたが、そこで拉致問題が疑惑ではなく実際に発生した事件であることが明らかになると、北朝鮮に対するイメージはさらに悪化することになった。
以降、日本社会における北朝鮮のイメージは、核問題も加わっており、良くなることは考えにくい。冷戦後、日朝関係における韓国の影響はほとんどなくなったが、それは日本社会の北朝鮮に対するイメージが悪化したためであって、たとえ日本政府が努力したところで、日朝関係はより悪くなることを避けられなかった。この状態は、おそらくこれからも続くことになるだろう。
「外交に関する世論調査」(内閣府)(https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-gaiko/zh/z19.html)(2022年2月11日アクセス)
「外交に関する世論調査」(内閣府)(https://survey.gov-online.go.jp/h12/gaikou_01/images/zu37.gif)(2022年2月11日アクセス